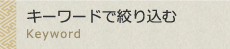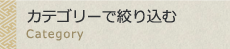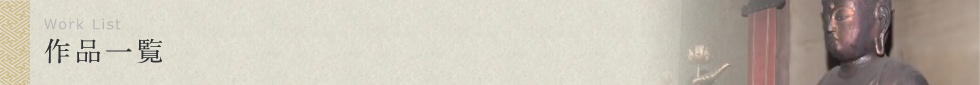一宮市・妙興寺(仏殿) 釈迦三尊像

| 種別 | Sculptures |
|---|
詳細
妙興寺は、一宮市大和町にある臨済宗妙心寺派の寺院である。貞和4年(1348)に滅宗宗興(めつしゅうそうこう)が亡き両親の恩に報いるために開いた寺で、正式名称を妙興報恩禅寺という。妙興寺は創建以後、北朝・足利氏の庇護を受けて発展したが、応永年間の火災で当初の建物の大半が焼失、その後、豊臣秀吉もしくは秀次の庇護を受け、寺は再興された。明治23年(1890)の火災では仏殿、開山堂、客殿、庫裡などが焼失したが、寺には現在も創建当時からの足跡を伝える数多くの文化財が残されている。
現在の仏殿は大正14年(1825)に再建されたもので、天井には西洋画家・山喜多二郎太(やまきたじろうた)が描いた油絵の蟠龍図を見ることができる。仏殿の本尊は南北朝時代に制作された釈迦三尊像(一宮市指定文化財)である。釈迦如来の向かって右側に普賢菩薩坐像、左に文殊菩薩坐像が安置されている。
釈迦如来坐像は、高さ93.0㎝。肉髻相、螺髪、肉髻珠、白毫相をあらわし、衲衣と裙を身につけ、左足を上に蓮花座の上に結跏趺坐する。両手は右手を左手の上に重ねる定印をあらわしている。金色の姿は金泥によって表現され、衣には盛り上げ彩色や切金文様による装飾が施されている。目には玉眼の技法が用いられている。光背には大日如来を納める宝塔の他、飛天、迦陵頻伽があらわされ、本像が制作された背景には禅の思想だけではなく、密教思想や阿弥陀浄土信仰も存在したことが窺える。
普賢菩薩坐像は、高さ58.1㎝。六本の牙をあらわす白象の上に、右足を上に半跏趺坐するが、左足を外す姿で表現されている。髻を結い、宝冠や瓔珞を身につけ、右手に如意を持つ姿であらわされている。普賢菩薩は、六牙の象に乗ってあらゆる場所に姿を現し、人々を教え導く菩薩とされている。
文殊菩薩坐像は、高さ58.4㎝。獅子の上に右足を上に半跏趺坐している。普賢菩薩と同様に髻を結い、宝冠や瓔珞を身につける姿で、右手に剣、左手に経巻を持つ姿であらわされている。文殊菩薩は、智恵をつかさどる菩薩で、大乗仏教における「般若」の教えを広め、実践する菩薩とされている。二体の菩薩が身につける衣にも釈迦像と同じように盛り上げ彩色の装飾がみられ、銅製の光背には透かし彫りの優美な唐草文様がみられる。
この釈迦三尊像は、文殊菩薩の頭部内には南北朝時代の仏師・院遵(いんじゅん)の名前が記されていることが確認されており、普賢菩薩の頭部にも「院」の文字が記されることから、院遵ら院派仏師の手によって造られたことがわかっている。