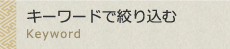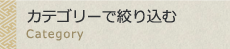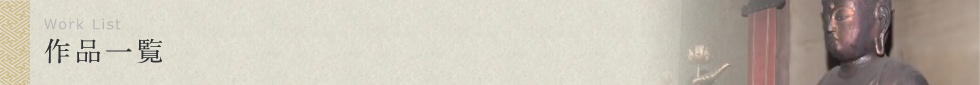稲沢市日下部東町 常楽寺の木造如来坐像

| 種別 | Sculptures |
|---|
詳細
稲沢市日下部東町にある曹洞宗の寺院・常楽寺の境内に建つ一堂に安置される木造如来坐像(137.8㎝)。常楽寺は天正19年(1591)に雄山源英によって創建されたと伝えられているが本像はそれより遥かに時代を遡る作品である。ヒノキと思われる材で造られた寄木造の仏像で、愛知県指定文化財である。稲沢市内には半丈六の大きさの如来坐像が点在するが、本像もその中の代表的な1体である。以前は体の表面に後補の漆箔が施されていたが、昭和49年に修理がなされ、現在はほとんど素地の状態になっており、一部に箔を残す。尊名は釈迦如来と思われるが、尊名の伝来も明確でないため、特定の尊名をつけない形で文化財指定がなされている。三道相をあらわす線が2本ずつあらわされる点や、大きな波のそばに鎬立つ小さな波を沿わせる古様な衣文表現など特徴が見られる。また、この像は像の内側から2種類の金属板を入れて目と瞳の部分を表現する技法が用いられていることが調査を通して明らかにされており、非常に珍しい造形がなされる作品でもある。この像は国分寺の仏像が洪水によって漂着したなど様々な言い伝えがあるが、寺に安置されるに至った経緯はよく分かっていない。