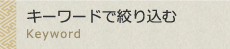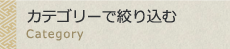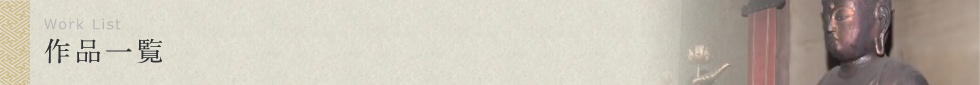稲沢市・松下町 観音寺の木造聖観世音菩薩坐像と木造地蔵菩薩半跏像


| 指定 | 稲沢市指定文化財 |
|---|---|
| 種別 | 彫刻 |
| 員数 | 2軀 |
| 大きさ | 木造聖観世音菩薩坐像36.5㎝、木造地蔵菩薩半跏像30.3㎝ |
| 素材 | ヒノキ材、寄木造 |
| 時代 | 永正12年(1515) |
| 所在場所 | 稲沢市松下町・観音寺 |

| 種別 | Sculptures |
|---|
詳細
観音寺は暦應元年(1338)大鑑禅師清拙和尚の開基と伝えるが、時代と共に衰退し、現在の観音寺の第1世となる名古屋総見寺13世靈源祖満和尚が再興し、第3世文翁義海和尚にかけて諸堂が再建されていったと伝えられている。濃尾大震災で諸堂は全壊し、明治35年から37年にかけて名古屋市東照宮の建物2棟を購入し、文翁和尚によって再建されたことが寺に残される棟札に伝えられている。本尊は金銅勢至菩薩立像(秘仏・高さ32.7㎝)で、鎌倉時代後期に造られたと考えられている。この菩薩像はもともとは善光寺式弥陀三尊の一体であったと考えられる。秘仏本尊の厨子の向かって右側に木造聖観世音菩薩坐像(高さ36.5㎝)が安置される。像内の墨書銘から永正12年(1515)に熱田の仏師・信教によって造られた作品であることがわかり、台座部分には慶応2年(1866)の修理記録も残されている。秘仏本尊の厨子の向かって左側に木造地蔵菩薩半跏像(高さ30.3㎝)が安置される。像内部の墨書銘から観音菩薩像と同様に永正12年に熱田の仏師・信教によって作られたことがわかり、また像内に慶応2年(1866)の修理記録も残されている。